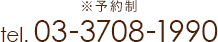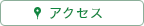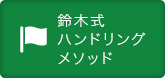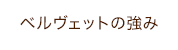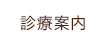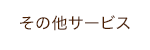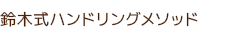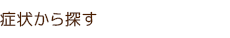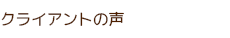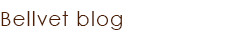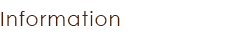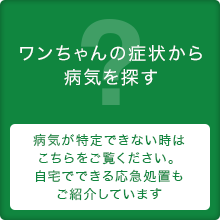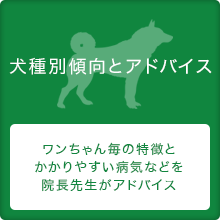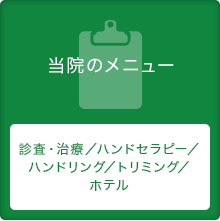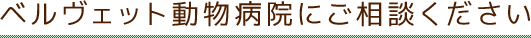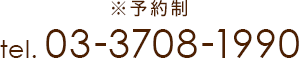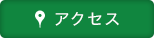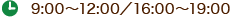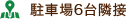鈴木式ハンドリングメソッド
私たちの獣医療は、動物とのコミュニケーションを中心に成り立っています。 診察と治療、その他犬と飼い主さんのケア、あらゆる面での核が「鈴木式ハンドリングメソッド」です。 当院では、どんなワンちゃんも診療台でじっとして、おとなしく獣医に診察させてくれます。 人が腕力で押さえつけることは一切なく、触診も注射もスムーズです。 「他の病院では、大暴れしたのに・・・なぜ!?」とびっくりする飼い主さんが度々いらっしゃいます。 そのヒミツが鈴木式ハンドリングメソッドにあるのです。 超能力などではなく、鈴木の経験に基づいて体系化したコミュニケーションの技術です。
※「ハンドリング」にはいくつかの意味があります。 私たちは「犬とともに生活する上での意思疎通、コミュニケーション」という意味で使っています。 動物が動かないよう人が身体を固定することを「保定 / ハンドリング」といいます。
人間でも病院の診療台に上げられると緊張するもの。
動物も同じで落ち着きを失って動く犬や猫を獣医さんが保定するのは 一般的な行為です。
動物が動かないよう人が身体を固定することを「保定 / ハンドリング」といいます。
人間でも病院の診療台に上げられると緊張するもの。
動物も同じで落ち着きを失って動く犬や猫を獣医さんが保定するのは 一般的な行為です。
 人と犬では身体のつくりが違います。
戦いなどで急所を隠すとき、人はふつう横を向きますが(ボクシングの構えのように)、犬は正面を向きます。
初対面の犬に人がいきなり正対すると警戒されてしまいます。
そうならないよう、私たちもまずは身体の側面を犬に見せて接します。無理に目を合わせることもしません。
アイコンタクトは、本来、注意をこちらに向けた犬の視線に人の視線を合わせることで、はじめて信頼が生まれます。
人と犬では身体のつくりが違います。
戦いなどで急所を隠すとき、人はふつう横を向きますが(ボクシングの構えのように)、犬は正面を向きます。
初対面の犬に人がいきなり正対すると警戒されてしまいます。
そうならないよう、私たちもまずは身体の側面を犬に見せて接します。無理に目を合わせることもしません。
アイコンタクトは、本来、注意をこちらに向けた犬の視線に人の視線を合わせることで、はじめて信頼が生まれます。
犬ではなく人をトレーニングする
 鈴木式ハンドリングメソッドは犬への「しつけ」ではありません。
例えば一般的な語学と同じような「人のスキル(技能)」です。
身につけるためには人がトレーニングしなければなりません。
人間以外の動物は基本的に「今」を生きています。
過去の記憶はありますが、犬の行動はその瞬間の人の態度や行動をそのまま反映していると考えてください。
どんなにやんちゃな犬も当院ではリラックスしてくれるのですから。
鈴木式ハンドリングメソッドは犬への「しつけ」ではありません。
例えば一般的な語学と同じような「人のスキル(技能)」です。
身につけるためには人がトレーニングしなければなりません。
人間以外の動物は基本的に「今」を生きています。
過去の記憶はありますが、犬の行動はその瞬間の人の態度や行動をそのまま反映していると考えてください。
どんなにやんちゃな犬も当院ではリラックスしてくれるのですから。
犬とあなたは「見える世界」が違う。どちらが合わせるのが早い?
 生き物の種によって世界の見え方・感じ方は違います。
私たちにとって、世界は豊かな色や質感を持っていますが、他の動物にはモノクロの線だけに見えるかもしれません。
多くの人は、「おすわりを学習させよう」「噛んじゃダメ!」など、犬に対して一方的に要求してばかり。
犬に対して人のコトバを理解させようとしているのです。
鈴木式メソッドでは人が犬のコトバを理解するよう努力します。
より賢いはずの人間が犬の見ている世界を理解するほうが犬に学習してもらうよりよほど簡単です。
生き物の種によって世界の見え方・感じ方は違います。
私たちにとって、世界は豊かな色や質感を持っていますが、他の動物にはモノクロの線だけに見えるかもしれません。
多くの人は、「おすわりを学習させよう」「噛んじゃダメ!」など、犬に対して一方的に要求してばかり。
犬に対して人のコトバを理解させようとしているのです。
鈴木式メソッドでは人が犬のコトバを理解するよう努力します。
より賢いはずの人間が犬の見ている世界を理解するほうが犬に学習してもらうよりよほど簡単です。
「ボス」ではなく「班長」であれ
 飼い主と犬の関係を語るとき、「上下関係」「主従関係」を明確にするべきだといわれます。
確かに犬がリーダーになると、家にいても、散歩をしていても、人を守ろうとします。
これは、犬にとっては大変なストレスで病気にもつながります。
人は、犬のリーダーであるべきです。
しかし、犬の社会のリーダーは、「ボス猿」のように絶対的な存在ではなく、他の犬を強い力で支配することはありません。言うなれば「班長」くらいの感覚。
人が無理矢理言うことを聞かせようとしても犬は理解できないのです。
飼い主と犬の関係を語るとき、「上下関係」「主従関係」を明確にするべきだといわれます。
確かに犬がリーダーになると、家にいても、散歩をしていても、人を守ろうとします。
これは、犬にとっては大変なストレスで病気にもつながります。
人は、犬のリーダーであるべきです。
しかし、犬の社会のリーダーは、「ボス猿」のように絶対的な存在ではなく、他の犬を強い力で支配することはありません。言うなれば「班長」くらいの感覚。
人が無理矢理言うことを聞かせようとしても犬は理解できないのです。
ほめるか、ほめないか
 班長は部下が少しくらい指示を間違えても、どなったり、手を上げることはありません。
鈴木式ハンドリングメソッドでも、犬をしかったり、まして叩いたりは絶対にしません。
良いことをしたときはそれと分かる方法で明確にほめます。
間違えたとき、意思疎通ができなかったときは、怒るのではなく「ほめない」だけで十分なのです。
班長は部下が少しくらい指示を間違えても、どなったり、手を上げることはありません。
鈴木式ハンドリングメソッドでも、犬をしかったり、まして叩いたりは絶対にしません。
良いことをしたときはそれと分かる方法で明確にほめます。
間違えたとき、意思疎通ができなかったときは、怒るのではなく「ほめない」だけで十分なのです。
すべてのベースは観察すること
 思えば私は子どもの頃から動物が好きで扱いにも長けていたようです。
特別な能力はありませんが動きを見る目がとても良いのだと思います。
自分がどんな態度、行動を示せば、動物がどのように動くのか。
些細な動きから、彼らのコトバを感じていたのだと思います。
鈴木式ハンドリングメソッドでも、まずは犬をよく観察することが大切です。
思えば私は子どもの頃から動物が好きで扱いにも長けていたようです。
特別な能力はありませんが動きを見る目がとても良いのだと思います。
自分がどんな態度、行動を示せば、動物がどのように動くのか。
些細な動きから、彼らのコトバを感じていたのだと思います。
鈴木式ハンドリングメソッドでも、まずは犬をよく観察することが大切です。
鈴木式ハンドリングメソッドは5つの分野で活用しています。
世田谷のベルヴェット動物病院の最大の強みであるハンドリングメソッドでペットが安心して診療できます
世田谷で口コミで人気の当院では院長をはじめ、スタッフがハンドリングメソッドを身に着け、ペットとのコミュニケーションにより信頼関係を築き、安心の診療やトリミングをお受けいただけます。
ベルヴェット動物病院の最大の魅力でもあるハンドリングメソッドは、診療や入院時にも活用され、初めての予防接種や辛い治療、飼い主様と離れての不安などを和らげたり、落ち着いて診療を受けたりして過ごすことができるようになります。
薬や器具を用いずハンドセラピー(整体治療)で痛みを取り除く手技療法もご提供しております。世田谷区で評判のハンドリングメソッドは飼い主様にもご指導しており、トレーニングを受けることができますので、ぜひお役立てください。